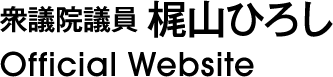私は、政治家として日本の原子力政策の「安全神話」作り上げてきた側の人間です。エネルギー資源の乏しい日本では、オイル・ショックが絶えず周期的に襲ってくることもあり、一時期、原子力発電に頼ってしのぐほかないと考えてきました。
それが、今回の茨城県東海村での「ジュー・シー・オー(JCO)」東海事業所(ウラン加工施設)の臨界事故により、四十年間かけて築いてきた原子力政策の「神話」がもろくも崩れたのです。東海村は私の地元であり、原子力政策を推進してきた私に対する信頼もあったと思いますが、もう「梶山さんが言うなら安全だ」と住民は思ってくれない。それほど住民の恐怖は強いのです。一番の原発推進派だった私でさえ、今回の事故の後ではニュートラルにならぎるを得ない。正直に言えば、手塩にかけてきたものにこんな形で裏切られるとは、という思いさえあります。
中央の起案者のいない避難命令
原子力発電の創業期には、官庁や企業には、間違っても事故を起こしてはならない、という一種の緊迫感がありました。それに、今までわが国での原子力の事故は本体の事故ではありませんでした。人為的な報告ミスとか情報の改竄は別として、原子力施設の中軸部分で軌事故はなかったわけです。
私も、重大な事故が起きるとすれば、原子力御三家といわれる日本原子力研究所や核燃料サイクル開発機構、そして日本原子力発電の三つであり、だからこそ安全の上にも安全を重ねていくしかないと思ってきました。だから、まさか、その周辺を支える民間施設で、こんな危機が起きるとは……。原子力発電の現状について、私自身がイロハのイを知らなかったと言われても仕方がない。しかし、茨城県知事も東海村の村長も知らなかったのです。もちろん、燃料棒の製造工場があるのは知っていましたが、規格に合った生産工程があるはずだと固く信じ込んでいました。これがいけなかった。慚愧に堪えない、とはまさにこのことです。
あの事故の日、私は出張先の大阪から午後五時四十分に衆議院議員会館に戻ってきました。ちょうど玄関先で科学技術庁の原子力局長に出くわしました。それで、彼が「万全の措置を講じています」と言うから、「そんな、万全なんて言葉、聞いてられるか。動燃の事故の時も万全と言ったじゃないか。オレのとこに来て万全と言う時問があるなら、あなたが現地に入って寝泊まりし、身をもって安全だと示したほうがよほどいい」と言ったんです。彼はいつも「安全だ」と言うのです。
翌日の朝、自民党本部で党の対策本部の初会合が開かれました。科技庁側は「(作業をしていた)三人はいすれも十数年の練達の技術者だ」と説明したのです。さらにわれわれ議員側から「原子力分野では、取り扱いの安全基準や従事する者の資格審査はどうなっているのか」という質問が出ましたが、結局、誰も答えられませんでした。
科技庁は何も準備していなかったのです。原子力安全委員会も通産省も含めて、中央の行政機関のどこも、地域住民に対する「半径十キロ以内の屋内待避」という命令を主導したところはない。つまり、中央省庁や行政機関には責任ある起案者がいなかった。「三百五十メートル以内の避難」を決めたのも地元の東海村の村長だった。本人が言っていましたが、「私がどうすればいいんだと騒いだら、三百メートル以内は中性子の影響が大きい、と説明されたので、それなら五十メートル足して三百五十メートルで、と思った」ということなんです。避難範囲に何の根拠もないとマスコミは批判しましたが、村長にそんな専門知識や科学的知見があるわけがない。現場が過剰反応するのは当たり前だ。しかも、科技庁はその命令の解除はしたのです。住民の安全に関する重要な避難勧告について、起案と解除の担当が別組織だったという点に、危機対応のマニュアルのなさが象徴されています。
大都市が安全ならいいのか
科技庁は監督官庁として、これまで、現地施設を視察してきたのなら、なぜ発見できなかったのか。ずさんな対応ばかりです。
これからは、何重もの安全策が必要です。このような事故が絶対起きないという保証がない限り、民間にはフリーに原発業務には従事させない。類似の事故を引き起こさないための装置を多重に義務づけ、運転マニュアルを整備する。さらに、それでも起きた場合には、とにかく初動対応のマニュアルが必要です。今回の事故でも、企業から科技庁など行政側には通報がなかった。「従業員が倒れたから来てくれ」という連絡だけだった。東海村の消防署には防護服もあるのに、それさえなしに救急車を呼んだのです。これでは科技庁にも、ましてや首相官邸にも情報伝達は見込めません。マニュアルがなければ、情報は企業から科技庁には届かない。ましてや官邸には伝えられない。それでどこが監督官庁なんですか。
もうひとつ、重要な点がある。今回、私は、原子力安全委員会は東京など大都市の安全を確認するだけなのか、という疑念を消せませんでした。私は通産政務次官になった一九七九年、東京に小型の原子炉をつくれ、と主張したんです。採算は度外視しても、それを実現すれば、何より原子力が安全であるとの信頼を得る証明になる。危険だからと東京が逃れることだけを考える原子力政策では、現実に原子力施設を抱えた地域を含めた国民全般の信頼は得られないのではありませんか。
「官」の立場では困る
さらに、ひょっとすると、科技庁があるから安全だと思い込んできたのが間違いだったのかもしれません。私は官房長官を辞めたあとで、アジア経済危機の際、いかに大蔵省から金融機関の不良債権の実態について知らされていなかったかを痛感したことがありますが、今回も科技庁が事故を想定しなかったと言うなら、監督官庁としての存在意義はありません。
それに、科技庁が仮になくなれば、地方自治体や民間が自分たちで施設の安全性を検証して、自己責任に基づいて判断するほかなくなるでしょう。が、私はこれから大都市・官側ではなく、現地・住民側の視点に立った原子力行政が必要だと思うのです。これまでの上からの安全基準はやはり、なるべくコストを安くし、安全面については本当に危険なことのみ排除するものでしかなかった。しかし、地域住民に判断を任せれば、厳しい基準を作ります。それでいいではないですか。少なくともそうした改革を図らなければ、失われた「安全神話」はよみがえりません。今回のような対応なら科技庁はないほうがいい。まさに非科学技術庁だ。それより住民側に高い安全基準のハードルを設けさせたほうがよほどよい。住民が多数決でノーと言えばダメです。市町村など自治体議会で賛成を取り付けなければ稼働できないことにすればいい。もう、地方と住民に任せてほしい。少しでも危ないなら止めます。
首相官邸で県知事、東海村の村長と一緒に有馬朗人・科技庁長官(兼文相、当時)と会った際も、有馬氏が「科技庁を挙げてきちんとした安全基準を作ります」と言うから、私は「官側の立場で考えてもらっては困る。これから私は住民側で要求します。住民がノーと言えば拒否権があるんです」と言いました。
私はもちろん、今ある原子力発電をすべてストップしろとまでは言いません。日本の電力消費の四割を占める原子力を止めるなら、電力消費やさらに現在の生活レベルを下げ節約する覚悟がないとできない。その運動もできず原子力発電だけを止めろ、と反対するのは現実的ではない。
しかし、これだけは言えます。これ以上、原子力発電を増やすという政策は無理だ。時間をかけ、民間を含めた下部組織から安全性を再構築し、総体として国民の信頼を得るほかない。それがないと、新しく原子力施設を増やすわけにはいきません。いけいけどんどんはダメです。
危機対応能力を奪った「占領ショック」
同時に私が痛感するのは、阪神・淡路大震災、ペルーの日本大使公邸占拠事件、アジア金融危機、そして今回の東海村の臨界事故と、九〇年代後半に日本を襲った危機はすべて通じるものがあるのではないか、ということです。現在の日本は、危機に対する感覚とその処理の能力をともに喪失したままなのではないでしょうか。
日本の政治や行政が危機管埋能力を失ったのは、私は敗戦後の占領が原因だと思っています。占領がすべて悪かったと言うのでばありません。財閥解体や農地改革など戦前の日本が果たし得なかった民主化や自由経済などに寄与した恩恵もありましたが、自ら危機を感じ対処するニつの能力を日本は占領時に放擲したのです。そして、日米安全保障条約の傘の下で経済成長を志向した。日本の平和と安全を米国に任せるという判断のなかでは、危機対応能力を再生することは米国への反逆を意味していたのですから。
自国の平和を他国が守ってくれるはずだ、と思いこむ幻想も一種の「安全神話」ではないですか。日本と米国の関係は対等であるべきですが、実はそうではありません。例えば、日米安保にしても、米国からみれば朝鮮戦争の際の行政協定はまだ生きている。現在休戦状態にある当時の国連軍が再び発動されれは、日本は何もかも米軍に協力しなければならないんです。日本と米国が外交的に対等であるというのは幻想なのに、日本だけが米国が日本を守ってくれると信じ込んでいる。そのため、日本が自ら危機に対応し、処理するという発想が成熟しないまま来たのではないか、と私は思うのです。
理念なき国家管理はダメだ
今年の通常国会では、周辺事態の際の米軍への協力を定めたガイドライン法や通信傍受法、国旗・国歌法などが成立しました。ただ、すべて各論です。各論だけ進むと、その部分だけは確かに補強されるが、その接合部分は弱くなってしまう。ましてや、総体は見えなくなってしまう。つまり、省庁の縄張り意識が強いなかで、省庁別の各論の法を整備する道を選ぶと、全体の危機管理の理念が逆に見えなくなってしまうのではないでしょうか。
私は、何か危機が起きれば各論的に対応していくやり方ではなく、まずは包括的な危機管理法という基本法を制定したうえで、首相をトップとする行政の危機対応の仕組みを作らないといけないと考えます。縄張り意識の残る縦割りの行政組織では、危機に迅速に対応できない。警察が自衛隊をコントロールできますか。海上保安庁が警察と自衛隊をコントロールできますか。東海村の事故で明らかになったように、官邸への情報伝達ひとつとっても、科技庁に何もかもやれ、というのは無理です。
それと同時に、危機に向き合う政治側の姿勢の問題もあります。私は古い人間ですから、太平洋戦争のことを持ち出しますが、当時の為政者は、欧米諸国の日本包囲網ができあがるなかで、座して死を待つよりは死中に活を求めるという思いであの戦争を起こしたのかもしれません。しかし、負けられないという思いが必勝不敗という本来、為政者が自己の意識としてはイコールで結んではならない信念に変わっていった。一般国民に必勝不敗を信じさせるのは現実政治として必要だったでしょうが、最悪の事態を想定して危機に臨むべき為政者が不敗だと本当に信じ込んだら終わりです。
それは今回の事故も同じです。国民ひとりひとりが専門家と同じ科学的知見を持て、というのは現実的でない。政治や行政に必要なのは、国民から信頼を取り付ける行為です。ただ、国民が「安全神話」を信じてくれるのは政治にとってはいいことですが、科技庁はじめ為政者、政治や行政のブロが、ただ安全を信じ込み、国民が安全を信じるに足る対応策を準備していないで、どうなりますか。
耐用年数という発想
ベルリンの壁が崩れ、ソ連が崩壊し、世界の米ソ二大陣営の対立構造が消えた九〇年代初頭、日本の政界ではいわゆる政治改革論争がありました。私はその当時、ソ連の崩壊で国際情勢や国際経済市場が流動化するから、政治・行政の危機対応力や情報収集力を強める改革が先決だ、と主張しましたが、現実には選挙制度改革が先行してしまいました。日本社会にはバブルの余波が残り、本業は陰りが見えていたのに土地売買で利益が出るという一見バラ色に見える情勢が続いていたせいかもしれません。
安全保障・防衛あるいは危機管理分野は米国に任せ、日本は経済成長だけを考えていれはよい時代は終わり、さらに各国や民族が自己主張を強める新たなナショナリズムの到来が迫っていたのに、日本政治の対応が遅れた。今から振り返れば、日本経済もその時期、実はバブルの清算と国際競争力の強化を迫られる瀬戸際にいたのです。まさに失われた九〇年代だったかもしれません。
東海村の事故を踏まえていま思うのは、原子力施設に耐用年数があるように、法律や国の行政制度にも耐用年数があり、無益有害となった制度疲労は避けられないということです。新幹線のコンクリート壁の崩落事故と同じです。
法律はすぺからく時限立法にしたらどうでしょう。一度決めたら法律や許認可が独り歩きし、逆に住民を支配する。しかも役人には、前例を踏襲する習性がある。一定期間を過ぎたら法律や許認可を見直すシステムを作らないと、日本人は惰性に流れてしまうのですから。
(1999年・平成11年「論座」12月号に掲載)