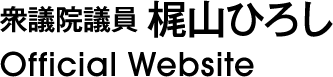はじめに
過去二年間の日本の政治は、「政治改革」の嵐に翻弄されてきた。私はこれまで時流の流れに乗った、実態論の伴わない「政治改革」を批判してきたが、政治の改革そのものを否定してきたのではない。東西冷戦構造のもと、戦後、半世紀近くにわたって続いてきた日本の政治の仕組み、とりわけ三十八年間に達した自民党による単独政権体制に綻(ほころ)びが見えていたのは事実だし、日本の政治、経済、社会のすべてが大胆な転換を遂げなくてはならない時期に達していたのは疑問の余地はない。問題だったのは、今日の日本を歴史的にどう位置づけ、何をどう変えていかなくてはならないのか、という明確な理念とビジョンを欠いたまま、多くの政治家が「政治改革」の旗振りに狂奔したことである。
選挙制度さえ変えれば、日本の政治が抱えているすべての病を根絶でき、二十一世紀に向けての理想的国家をつくる礎(いしずえ)となる、などと考えるのは幻想の最たるもので、どんな選挙制度にも完全な制度はない。私は日本における小選挙区制は、一党独裁政権の基盤となる制度にほかならず、今でも問題が多いと考えているが、すでに次の総選挙が小選挙区制で実施されることが決まっている以上、この制度に基づく日本の政治、経済、社会の改造を、真剣に押し進めるしかない。中選挙区が「ポスト冷戦」の時代にそぐわないものとして廃止されたように、もし小選挙区制が日本の平和と、安定的な発展に合致しないものであることが判明したなら、もう一度これを変えていく勇気を、政治家はもつべきだろう。
そのためにも、新選挙制度の実施を前に、今の日本に何が必要であり、何をどう変えるべきかという考え方を明確にするのは、政治家一人一人の義務である。不幸にして、日本の政界は依然、積極的なビジョンを推進するだけの安定を見てはいない。一刻も早い政局の安定は、大胆な政策遂行のためにも急務であり、「野合」などといわれながらも、私が自社さきがけ連立政権をいささかなりとも推進した理由もそこにある。しかも社会主義の崩壊を見るまでもなく、自社両党の間に、政治基盤の違いはあっても、政策の違いは極めて小さなものになっているとの判断があった。いわゆる五十五年体制の時代から自民党は社会党の主張する高福祉、労働者・消費者重視の政策を取り入れ、社会党もまた、イデオロギー一辺倒の政治姿勢から現実的、漸進的な政策論の道標を拡大してきたのである。
村山首相は九十四年夏の就任早々、自衛隊の合憲をはじめ、歴史的ともいうべき社会党の基本政策の転換を行なった。五十五年体制の実質的な崩壊は、自民党の単独政権が崩壊した九十三年七月ではなく、村山首相の方針転換をもって完了したとみるべきである。これからの政治体制がいかなるものであるにせよ、確かなことはイデオロギーを中心にした政治勢力の色分けでなく、何をなすための政権か、という明確な指針に基づくものでなければならないことは言うまでもない。私はこの二年間、単独政権崩壊時の自民党幹事長だった責任とけじめのため、戦犯を以って自らを任じ、政治家の初心に立ち返って、今の政治が何をなすべきか、これからの日本がどうあるべきかを考えてきた。この機会に、その一端を明らかにしてみたいというのが本稿の目的である。
1. 健全な社会
経済発展で失ったもの
戦後五十年、日本が経済国家として、歴史上、例を見ない成功を収めたことは間違いない。親より子、子より孫の世代の方が、豊かで明るく、恵まれた生活を謳歌できるという未来への期待を日本人が持てるようになったのは、長い日本の歴史の上でも、おそらくこの半世紀足らずのことにすぎない。この「未来への期待」こそが、経済国家としての成功の成果であり、新たな発展の原動力でもあった。敗戦による国土の荒廃をこの目で見て、果たして日本は再び立ち上がれるのだろうかと、暗憺(あんたん)たる気持ちで外地から故郷に戻った私にとっては、「よくぞここまで」という感慨を、いまだに禁じ得ない。
ところが今、われわれの孫の代の日本が、本当により良い国になっているのか、その次の世代はさらに素晴らしい社会に生きられるのか、と問うた時、果たしてそうなのか自信をもって答えられない状況になっている。最大の理由は、なんといっても経済の限界、経済成長の頭打ちに起因するものであろう。バブル経済の崩壊は、一時的な繁栄の高いツケとなって、われわれ日本人の自信を必要以上に喪失させてしまった。しかし、そればかりではない。奇跡的ともいうべき経済成長と引き換えに、われわれはもっと大切な何物かを忘れてきた、あるいは失ってしまったのではないだろうか。それは、一言でいうなら日本人としての道徳律であり、それを支えてきた歴史観や家族制度である。円高による国内産業の空洞化がますます深刻になっているが、実は「心と産業の空洞化」が共に進んでいるのである。
今、日本がなさねばならないことが、政治、経済構造の大胆な転換と同時に、社会そのものを改革すること、すなわち政治、経済、社会が常にバランスを保って発展できる「健全な社会」を再構築することではあるまいか。日本にとって、残された時間はそう多くはない。私は、ときに焦りにも似た不安に襲われてならない。
「日本型経済成長」の時代は終わった
日本の経済成長は、良いものを安く、大量に作り、広範囲に売りさばく「ハード主義」「大量生産・大量販売主義」に依ってきた。これを可能にしたのが、米国が圧倒的な経済力をリード役としてきた資本主義経済の拡大と、世界の半ば近い地域を低成長、自給自足的な制限的経済圏に封じ込めた社会主義体制の存在だった。米ソの冷戦構造が崩壊し、米国経済も昔日の勢いを失って久しい今日、日本経済が抜本的な転換を迫られているのも、致し方のない試練ともいえる。
この試練にあたり、政治家も経済人も官僚も、明快な処方せんを示せないでいるのには、相応の理由がある。日本を取り巻く経済環境が安定さえしていれば、「ハード主義」「大量生産・大量販売」という方法は、政治家、経済人、官僚のいずれにとっても、最も手段を講じやすい一本道だった。政治が資本の拡大再生産にとって最善の道を立法と行政で実現し、専門知識をもった官僚がこれを補佐する。経済人は自らの才覚を駆使して、おのおのの企業を発展させる、という構図である。ところが、現在の転換期にあたっては、この十八番の一本道は通用しない。採るべき道がないのではなくて、道が極めて多種多様なうえ、その効果も未知数であるために、政治家も経済人もパワーを結集できないでいるのである。そこで私は、現状の問題点の根本を正すことを第一とし、いくつかの提言をしてみたい。
経済国家から道義国家へ
「日本人は、水と安全はタダと思っている」とは、しばしば指摘されるところである。最近では、ミネラルウオーターも普及しているし、凶悪犯罪も増えて日本社会の安全神話にも翳(かげ)りがみえているから、この2点においては世界の常識に近づいているといえるかもしれない。しかし、水や安全にも増して、日本人が空気のように当たり前のごとく、アプリオリに存在するものと信じて疑わなかったのが、ある種の道徳律である。私は戦前のごく平均的な農村家庭で生まれ育った。家には厳格な祖父母と両親、9人の兄と姉。おそらく先祖代々がそうであったように質素、倹約、勤勉を美徳とし、国や社会へのなにがしかの貢献で名誉を得ることを家の誇りとする、そんな風土だった。戦後の高度成長を支えた日本人の多くを育てたのも、同様の風土である。
ところが戦後の急速な経済成長と、何事も経済的な視点からのみ判断を下す経済偏重の潮流は、日本を農村国家から都市国家に、家庭を大家族から核家族へと変ぼうさせたばかりでなく、日本人が脈々と受け継いできた倫理感、道徳律をも喪失させた変形国家に変えてしまった。社会全体が健全な精神、健全な理念と活力を持つことは、国家が国家として存在し、繁栄していくための最も基礎的な条件である。戦前は、道徳律を国家が規定し、管理しようとしたために、軍部独裁という弊害を生み、かえって国の繁栄を阻害してしまった。
政治がなさねばならないことは、道徳律の規定、管理ではなく、国民個々人が自らの内なる道徳律を大切にし、社会全体がそれを価値あるものに高めていくために、勇気をもって取り組んでいくことだ。すなわち、繁栄した「経済国家」であることを誇る前に、「道義国家」であることを目指すべきである。これは一義的には、日本の社会、家庭、教育のあり方の問題だが、真の国際国家として、アジアなどへの貢献策を推し進めていく際にも、基本となるべき国のあり方だと思う。
第一歩は教育改革
「道義国家」への第一歩として、教育改革の必要性を指摘したい。地下鉄サリン事件にみられる無差別、凶悪事件の発生や、その背後にあるオウム真理教の一連の問題は、今の日本社会が抱える不健全性の象徴である。オウム真理教の幹部といわれる人間が、いずれも高学歴で、入信前は「まじめ、努力型」の若者だったとされている点にも注目する必要がある。しばらく前から、経済界の方々と話をすると、必ずといっていいほど、理工系大学の不人気と学生の減少が日本経済のファンダメンタルズを弱めているのではないか、という問題が話題になる。健全な社会な社会であれば、その専門知識を生かし、国と社会へ大きな貢献をしたであろう若者が、新興宗教に魂の救済を求め、ついには人間として許すことのできない反社会的行動に走った事実を直視しなくてはならない。
そこで採るべきは、知識偏重の詰め込み型の教育から心、体、智が一体となった人格養成型の教育への転換である。そんなことは言い古されたことで、現在の受験システムと学歴社会がある限り、お題目にすぎないといわれるかもしれない。そこで逆説的に聞こえるかもしれないが、才能重視の教育を推進するシステムを具体化するのも一案だ。公立の学校教育が、平等主義の名のもとに画一的な教育をしているのにすぎないのなら、一人ひとりの青少年がもつ才能は一向に開花しない。のみならず、平等主義の補完機能として、受験産業や、予備校のように一流大学への進学だけを売り物にする私立校を増殖させるだけである。
才能教育というと、かつてのソ連など旧共産圏にみられた国家管理型のエリート教育や、フランスのような伝統的エリート社会のそれをイメージする向きが強いかもしれないが、私の主張はそうではない。ここでいう才能教育は、もちろん理工系、文学、芸術、スポーツなどあらゆる分野で、個々人の能力を最大限に引き出そうとするものに変わりないけれども、「多様な価値観を尊重すること」と、個々人の選択肢は「幅広く、変更も自由」なものとするのが大原則である。
多様な価値観を尊重する、というのが、どの分野に優れた人間を尊び、どの分野を軽視する、という差別のないことはもちろん、大学の入学基準も、あらゆる側面の能力を重視し,バランスのとれたものにすることだ。そして、自らの才能を伸ばそうとする分野の選択肢は可能な限り広くし、その分野を固定することなく「変更自由」の柔軟性を確保しなければならない、ということである。
青少年の「才能」として尊重すべきは、学力ばかりではない。先の阪神大震災で、国民の多くが感銘したもの一つに、若者のボランティア活動がある。自らの家も焼け、通学もままならない若者が、リュックサック一つで避難所に駆けつけ、被災者が救援にあたった姿に、日本もまだまだすてたものではない、と感じた国民は多いはずだ。
ところが、こうした若者らしい正義感も、これを受け入れる成熟した社会と、システムがなければ、時として不幸な結果に終わることもある。被災者の生活に落ち着くにつれ、一部のボランティア同士、あるいは地域社会とのいざこざが指摘されたのも、それゆえであろう。
日本の国内ばかりではない。日本が初めて自衛隊のPKO部隊を派遣したカンボジアで、尊い命を散らせた中田厚仁君のように、アジアでもアフリカでも、正義感と情熱をもって青春を燃焼している若者がたくさんいる。ところが残念なことに、彼の活動と、その経験を「日本の財産」として大切にする環境に欠けているのである。「多様な価値観を尊重する」教育の中では、ボランティアのような社会活動の能力、実績も十分、評価していくべきだろう。
当然のことながら、教育は学校の制度、仕組み、内容によってのみ完結し得るものではない。より重要なのは家庭と社会における教育であり、青少年の人格は、この二つと学校教育が役割を分担し、互いに密接な関連を保ちながら、形成されていく。ただ、どのフィールドにおいても、共通して重要なことは、善悪の区別をきっちりと教えることであり、これが道徳教育の基本である。天上の星と心の内なる道徳律は普遍、不滅であり、それが個人の領域に属することはいうまでもない。しかし、このことは家庭や学校が、善とは何であり、悪とは何かを教え込むこととは決して矛盾しない。
かなり以前から学校の校則の厳しさが問題となっていて、中には「デザートを主食の前に食べてはいけない…」といったものまであるのだそうだ。食事のマナーはマナーとして大切なことではあるが、それは校則で規定するのではなく、両親や先生が日常の中で教えるべきことである。家庭や学校が道徳として教えるべきは、もっと根本的な善悪の区別であり、しかも「してはならない」という抑制的なものより、「すべし」という積極的な「善」であるべきではなかろうか。
そのうえで政府は、国としての立場から善悪の区別を明確にした行動をとらねばならない。すなわち法と国民の常識と社会的良心に照らして、善いものは徹底して勧め、悪きものは罰する。つまり国と社会はイデオロギーや余計な思惑に関係なく、確固として善悪の理念の行動を通じて提示し、個人は個人で各種の教育の場を通じ自らの道徳律を確立するのが理想である。
論語に「君子喩於義、小人喩於利(君子は義に喩(さと)り、小人は利に喩る)」という言葉がある。物事を処理するにあたって、君子はまず自分の行動が義、すなわち公の考えを持っているかどうかで判断し、小人は損得勘定で考える、の意である。経済国家としての日本が、国中、あるいは国家そのものが小人になってしまったことを、今、改めて考え直さねばならない。確かに経済は、人間を幸せにする最高の手段かもしれない。しかし、あくまで手段にすぎないのにもかかわらず、その手段が目的となってしまったことに日本の危機がある。
道義なき国家、社会は、つまるところ衰退に至る国家だ。日本人一人ひとりが「プライドを持って恥を知る」日本の伝統を、もう一度、噛み締める必要がある。そのためには、道徳律を備え、自己の能力を最大限に伸ばした人材を、あらゆる分野にわたって育成していくことが、日本の活力を再生させるためにも焦眉の急である。
2.絶対的平和主義
道徳律が一見、目にみえないけれども、「健全な社会」を担う礎(いしずえ)だとしたら、厳密な形をもって国の基本をなすのは、憲法である。戦後五十年の節目にあたって、いままた憲法論議が盛んになっていることもあり、この問題を抜きに日本のビジョンは語れない。
私は日本国憲法が不磨の大典だとは思っていない。国の基本である憲法を不可侵のものとして神棚に祀るのは、そもそも民主主義には不可欠な柔軟性に欠けるし、国際情勢がこれだけ大きな変化を遂げている中で、国民が常に憲法のあるべき姿を考え、より時代に即したものにしていく努力が必要である。ただ、現行憲法が終戦直後の混乱期に、米国案を下敷きに作られた経緯などを強調するあまり、これが戦後の日本の発展に寄与してきた役割をも過小評価する意見には同調できない。
特に「戦争の放棄」をうたった第九条は、何百万人に及ぶ日本人の血で購(あがな)った条文であり、この精神をむやみに変えるべきではない、と考えている。九条に代表される憲法は、戦争に敗れた日本が、軍国、大国主義路線を棄て、国が小さくとも国民が安心して平和に暮らせる文化国家として歩んでいくことを、内外に宣言したものであった。幸運にも経済国家として、戦前以上の繁栄を謳歌できるようになったが、日本が平和主義を誓ったその原点を忘れてはならない。
例えば、国際貢献を積極的に進めるためには、現行憲法に基づいた自衛隊の活用には限界があるとか、そもそも日本が国家固有の権利としての自衛権を放棄したものではないことを明確にすべきだ、といった議論もあるが、こうした議論と九条の理念を大切にすることとは別問題である。日本が戦争放棄を宣言したのは、再び戦争をしない平和国家となる決意を明らかにしなければ、国際社会の中で、独立国として生き残れなかったからである。
日本が海外からの侵略の危機に直面し、危急存亡の時を迎えているというのならともかく、経済的に大きくなったからとか、「世界の常識」を超えた九条を変えることで日本人の主体性を示すべきだ、といった自らの事情で、今さらその原点を変えるのは許されないのではないだろうか。諸外国も九条の変更を望んでいない以上、無用の警戒心を引き起こすだけである。国際情勢がいかに大きく変化しても、日本は国際平和の中でしか生きてはいけない国であることを忘れてはならない。
3.アジア重視
「顔」のない国家の「第三の開国」
戦後五十年の歴史の中で、日本という国家が忘れてきたものは、国際社会における「顔」という面でも同様である。日本が何を目指し、何をどうしようとしているのか。それが分からなければ、経済力で伸びた身の丈が大きい分だけ、諸外国から不気味に見えるのも無理はない。冷戦構造のもとにあって、日本の外交路線は「対米重視」、極論すれば米国一辺倒を貫いてきた。それ自体は決して間違った選択ではなかった。しかし、冷戦構造が崩壊し、米国の世界戦略が変化を遂げている中にあっても、日本に新たな外交理念を生まれていない。それのみか、これまでと変わらない対米思想を墨守しているがために、米国の一挙手一投足を見て、「日本いじめ」とか、「対日圧力」だと過剰反応する。米国の方が変化しているのである。国家と国家が互いに自国の利益を追求し、外交術の限りを尽くすのはいわば当然であって、日本も個別の利益と国家全体の利益を重ね合わせながら冷静に物事を判断しなくてはいけない時期にきている。
私は今の日本が、幕末のペリー来航、昭和二十年の敗戦に続く、「第三の開国」期を迎えているのだと思っている。経済成長のみを国家発展の唯一の基準とし、明確な外交ビジョンを持たずに済んだ日本が、真の国際化を迫られている「開国」である。ペリー来航のころの日本には、武家社会、鎖国主義という顔があり、敗戦時の日本には軍事国家という顔があったからこそ、国際社会で生き残るために別の顔をつくり得た。
では「顔」のない今の日本が採るべき開国の基本方針は何か。私は、日本がアジアの一員として、アジアの人々と苦楽を共にすることと、徹底した国際貢献であろうと思う。
アジアの一員として
日本外交を二国間ベースでのみとらえれば、ポスト冷戦の今日でも、政治的、経済的に最も重要なのは、日米関係であることに変わりはない。地球規模の国際問題を自国の問題として取り組める国家は米国をおいてほかにないし、米国の自由主義、民主主義の理念は、依然、国際的に普遍性を持っている。極東の平和と安全にとって、中心的な役割を果たしてきた日米安保体制は、今後も大切であり、これからますます重要となる地域安全保障の根幹をなすものである。それだからこそ、米国が内向き志向に陥らず、重要な国際問題でイニシアチブを発揮していくよう、日本として可能な限りアシストしていかなければならない。経済の側面を見ても、良好な日米関係は、世界経済の安定的な発展に不可欠であることを常に肝に銘ずるべきである。
ただ同時に、日本が歴史的にも地政学的にも、アジアの一国としてしか生きてはいけないことも明らかだ。「アジア重視」は、日本外交の言い古されたスローガンであるが、実態として、日本政府がどれほどその重要性を国民に説明し、実践しているかといえば甚だ疑問である。加えて、日本がいくら「アジア重視」と叫んでも、様々な場面で、それが対米関係という基盤を前提とした二次的なものといった印象を与えることすらあるために、アジアの人たちにはなかなか信用してもらえない。このままでいると、日本はアジアでも、ましてや西欧でもない、国際的にも中途半端な経済国家として孤立しかねない危険をはらんでいる。
ところが経済国家としては、わが国は、すでにアジアと切っても切れない関係になっているのである。日本の全輸出額に占める対アジア貿易の割合は、九十四年で三九・七%。対米の二九・七%を大きく上回っている。十年前と比べると、対米が七・五ポイント減少しているのに対し、対アジアは二〇・八ポイントも急増した。日本への輸入額を見ても、米国の占める割合はこの十年間で二・九ポイント伸びて全体の二二・八%。アジアからは一一・三ポイント増の三四・七%に達している。貿易額自体が、十年間に輸出で二・二倍、輸入で二・一倍も拡大しているのだから、アジアとの貿易量の急進ぶりは驚くばかりだ。プラザ合意を契機とした急激な円高が、日本企業のアジアシフトを一気に促したことが主因だろうが、P・ドラッカー教授の言葉を借りれば「十年前、アメリカ人の言い方だと、日本が『片肺で飛ぼう』としていた。しかし、今では両肺で飛んでいる」。つまり、米国とアジアは、日本にとっての二つの肺なのである。
にもかかわらず、アジアが日本にとって死活的に重要な地域であるとの認識が、まだまだ深まってはいない。アジアの一国である日本と、他のアジア諸国を隔てている壁は、一義的には過去の戦争かもしれない。その国民感情を埋めていく不断の努力を、今後も真摯に続けていかなければならないことは言うまでもないが、アジア諸国との良好な関係が日本の将来にとっていかに重要かという認識を、国民レベルで深めていくことも同様に大切である。
その認識の深まりがないまま、経済関係のみが突出的に強まっているために、アジアの一部はもちろん欧米人すらも指摘する「日本の経済侵略」という誤解に、効果的な反論ができない。日本の経済は、アジアとの関係を強めなくては維持できない構造になっており、それは「経済侵略」ではなく、共生の道でしか永続性を持たないことを訴えていくべきだ。そのためにも、次に挙げる国際貢献も、アジアの人々が十分に裨益(ひえき)するものでなければならない。
4.国際貢献を国家目標に
貧困の哲学から富裕の哲学に
長く貧しい刻苦勉励の道を歩いてきた日本人が、貧困の中でも人がいかに人間的に、美しく生きるかを考えてきた民族だったのではないだろうか。ところが今や日本人は、世界的にも有数の富める国民になったにもかかわらず、裕福なものは何をなすべきか、国家はいかにあるべきかを依然、はかりかねているように見える。私は世界の平和と繁栄に対する徹底した貢献こそ、富裕国となった日本のとるべき道だと思っている。もちろん軍事力を背景とした平和創出とかいった類のものではない。日本の技術力と経済力を総動員することで、国際社会から真に評価される方法を採るべきである。
国際貢献は、諸外国のためばかりではない。日本の唯一の国家目標だったともいえる経済発展が成果を収め、壁に突き当たっている今日、日本人が新たな夢と希望を抱き、国際社会で誇りをもって生きていく糧にもなる。さらに、それは日本の次なる発展に資するものでもある。その具体策として、二つの国家プロジェクトを提言してみたい。
エネルギーと食糧は永遠か
国際貢献と、日本の将来の姿をリンクして考えた場合、私は日本をハード中心の量産型社会から、先端技術を核としたソフトとこれまで得意としてきたハードを混合した、柔軟な技術立国に変え、その成果を国際社会に還元していくべきだと思う。具体的なプロジェクトの第一は、自然エネルギーの変換・輸送・貯蔵に関するものである。現在の生産量を基準にして、石油の可採埋蔵量は四十六年、天然ガスが六十五年と試算されている。世界経済の成長に伴い、これも加速度的に減少していくだろうし、このまま化石燃料を燃やし続ければ、地球の温暖化も深刻になる。
そこで私は、国会議員としてエネルギー問題に携わり始めた二十年前から、太陽光のエネルギーを何とか活用できないかと考えてきた。地球の砂漠にふりそそぐ太陽光のエネルギーは、毎年、電力換算で四京三〇〇兆キロワットアワーと天文学的である。二十年前には、太陽光エネルギーを使用可能な形に変換することも、砂漠から転送することも夢物語だったが、今や必ずしもそうではない。発電コストの低下、電気を液体水素に変えての輸送や超伝導送電技術の進歩、超電導コイルや高効率の蓄電池の開発などで、太陽光エネルギーの大胆な活用の方法もおぼろげながら見えてきた。また、世界の未開発の水力エネルギーは、現在の世界の電力消費量(約一二兆キロワットアワー)に匹敵するとされるが、蓄電技術の進歩は、この有効利用にも道を開くとみられている。
人類にとって、もう一つ深刻なのは、食糧問題である。二〇五〇年の人口は、このままだと現在の約二倍、全世界で百億人に達すると試算されている。百億人の人間が一日三〇〇〇キロカロリーの食料を摂取するためには、少なくとも今の二・三倍の食糧生産が必要になる。一方では農地の砂漠化や土壌の劣化による収穫の減少という事実がある。そうなると、科学の力で食糧の増産を図るしかない。
その第一は、バイオテクノロジーによる遺伝子組み換え技術の開発だ。病気や雑草に強い稲を作り上げれば、農薬による土壌汚染も防げるし、厳しい発育環境に耐えられる稲やその他の食糧の誕生は耕地面積の拡大につながる。バイオマス技術は未利用資源の食糧化や、より効率的な魚類の生産にも応用できる。
もう一つは、植物の工場生産である。培地、肥料、日照などの環境制御と品種改良で、一年に一作の食物を三~四作、しかも、二層三層にして栽培することも可能だ。
二十年・五十兆円のプロジェクトに
エネルギーと食糧の問題は、いずれそう遠くない時期に、危機的な状況が訪れることを多くの人々が知っているにもかかわらず、誰も大胆に手をつけようとはしない。しかも、今でも八億人近い人々が栄養不足状態にある発展途上国の人々にとって、この二つは一部先進国が資源と富を独占し、豊かな生活を享受しているために深刻化しているのだという思いが強い。ところが、政治は目先の危機に対応するので精一杯だし、企業だけでは採算が合わない。ただ、危機が現実のものとなってからでは、すでに遅いのである。
米国は人間を月に送り込むアポロ計画に九兆円を投じた。私は二つの国家プロジェクトに、二十年間で五十兆円規模の投資を行うべきだと思う。研究分野への大胆な投資は、周辺技術への波及も促すし、様々な分野の研究者を育成する効果もある。国債が将来への投資であるとするならば、子孫の生存に直結するこうした分野にこそ、意を決して使うべきだろう。開発によって得られるエネルギー、食料、そして技術やノウハウを、すべて対外的に公開すれば、アジアをはじめ途上国の人々に対する大きな貢献となる。
結び
私があえてここに一文を物したのも、政策の対立軸なき時代にあって、誰も本気で政策論争する雰囲気が、ますます希薄になってきたからである。しかし、これからは政治家自身が具体的な政策テーマをより明快に掲げ、それを実現していかなければならない。冒頭、触れたように、新たに導入された小選挙区制は、一党独裁を招きかねない制度である。その中で、与党であれ野党であれ、政党が政党としてのアイデンティティーを維持し、同制度の謳い文句通り「政策論争を戦わす二大政党制」を実現するためには、国民の前に明快な形で政策を明らかにし続けることだ。
私の小論の内容については批判も受けたいし、改善もしたい。政治家を含む国民のすべてが二十一世紀に向けたアイデアを持ち寄り、一つずつ、少しずつでも実現していくのが、私の希いである。
(1995年・平成7年6月発表)