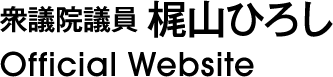(1999年(平成11年)「文藝春秋」6月号に掲載)
ずいぶん昔の話だ。昭和三十七年頃だったろうか、全国の若手地方議員からなる青年議員連盟の一員として、米国から中南米へと旅したことがある。当時、大阪府議会議員で同連盟の会長だった中山太郎さんも一緒だった。私は欧州に向かった一行とメキシコで別れ、再び米国に戻って、二週間近くにわたりテキサス、テネシー、ケンタッキーと民家にホームステイして回った。平均的な米国人の生活を体験してみようと思い、在日の米国人宣教師に頼んで受け入れ先を紹介しておいてもらったのである。
まだ、日本人の海外旅行も珍しかった時代、そこでの印象は強烈だった。週末には郊外の湖にサンドイッチを持参してピクニックに出かけ、日曜日は家族で教会に行き、ボランティアに励む。夜になれば、主人がギターを弾き、一家そろって団欒を楽しむが、家の中での子供の躾は実に厳しい。教会と社会に奉仕する義務感と、倫理観が自然と教え込まれ、やがて自立した米国市民となる素地が育まれていく。その素朴な生活の核となっているのは、宗教である。彼らの宗教は極めて厳格で、時には宗教戦争になるような過激な面もあるが、豊かさの中での私と公のバランスをとっていく規範となっている。
一方、日本の宗教はというと、一部を除けば、歴史的に緩やかで、普段の生活や社会に対する義務を自ずと規定するといったことはほとんどない。私と公のバランスをいかにとるかは、ひとえに個々人の意志と良心に委ねられているのである。これは個々人にとっては、非常に難しい問題で、貧しさが深刻になれば公による集団的な過激思想、つきつめれば戦争といった事態を招くこともある。反面、豊かさを享受し続ければ、公の論理をとことんまで排除し、自分だけよければいいという利己的な個人主義に陥りかねない。米国で例にあげた「豊かさの中での私と公のバランス」をとるのは、どんなにそのバランスをとろうとする優れた個人がいたにしても、社会全体にその風潮が生まれていなければなかなか難しいのである。すなわち、宗教のような生活規範のほとんどない日本人が、市民として自立していくためには、米国市民よりはるかに辛い、不断の努力がいるということだろう。
「自分の国は自分で守る」という常識
この数年、私の頭を捉えて離さないのは、日本人の自立、日本の自立といった問題だ。何度かにわたって金融や産業政策、沖縄問題などに関する論文を発表してきたが、最後には必ず、この問題にたどり着く。今回、私が日本の安全保障・危機管理について稿を起こそうと思い立ったのも、こうした問題を抜きに日本の自立を考えることはできないからである。
一個人を考えた場合、自立とは、社会への責任と義務を果たしうる能力と自覚を備えていることを指す。人間というのは、元来、集団生活にもっとも適した生き物であって、個人が生存し、充実した生活を保証される最適の環境を得るために、集団を作り、ムラを起こし、そして国家を形成した。国家はその個々人の生命と財産を守り、さらにはできるだけ豊かな社会となることを追求するから、本質的には利己的な存在にならざるをえない。ただ、今のように総体としては秩序が保たれている国際社会にあって、自己の利益だけを追い求める行動は、結果として自己の不利益につながる、「ネット・マイナス」になることが多い。それゆえにこそ、自立した国家ならば、その能力に応じて国際社会への責任と義務を果たし、共存共栄を図ろうとするはずである。
この意味において、日本は国際社会に生きる国家としての自立を、いまだに確立していない。先のガイドライン関連法案をめぐる論議は、まさにその典型で、1.自衛隊の対米支援は、米国による戦争に巻き込まれるものではないか。2.民間の施設を米国に提供する行為は、国民生活を脅かすものではないか。3.近隣の大国である中国の反発を招くのは、外交的にマイナスではないか--といった諸点に、関心が集中した。ここでは、本来、安保の基本である「自分の国は自分で守る」という常識が、完全に欠落している。
手を拱いて何もせず、平和を祈るだけで日本の安全が保障されるなら、それに越したことはない。橋本内閣の官房長官時代、私はしばしば有事法制に言及して物議をかもしたが、その折、ある党の人に「梶山さん、政治家は無事を祈っていればいいんだよ」と言われたものである。しかし、平和で冷静な時期に、最悪のケースを考えておかなければ、超法規的な措置ですべての事態に対応せざるをえなくなる。現にガイドライン論議のさなかでさえ、「現実的には、具体的な危機が起こらなければ日本は何もできない。逆に、危機が起こりさえすれば、すべての問題は一瞬のうちに片づく」といった超法規的措置、あるいは緊急立法への待望論が、一部の政治家や役人の中にはあったのである。これは実に危険な発想だ。
私は常々、「臆病派」を自認しているが、これが程度の違いこそあれ、戦争を経験した世代には共通のものかもしれない。最悪を想定しなければ、どうしても心が静まらないし、次の行動もとれない。明日の命も定かでなかった時代の産物だろう。そして戦前の日本は、明日への備えもないまま、いってみれば超法規的措置を泥縄式に法制化していくことによって、最悪の事態に突入したのである。
愚かな歴史を繰り返してはならない。なぜなら、人間は歴史の教訓に学んで行動することが期待されているからである。反面、歴史に学ばないか、誤った教訓に従えば、過去の失敗を再び惹き起こすことになりかねないし、そうした例は古今東西にいくらでもある。そうならないためにも、今、この時期に安保を語ることは、私の世代の責任だと信じるのである。
重要なのは、平時に危機管理や安全保障の法整備を進め、理解を深めておくことだ。日本は半世紀にわたる太平に慣れてしまったのか、パニックに殊のほか脆弱な社会になってしまった。一昨年秋以降に相次いだ大型金融破綻への世論の反応はどうだったろうか。明日にも日本経済はつぶれかねないとの悲観論が日本中を覆いつくしていた。私もその直前に十兆円の新型国債を財源とする金融システム安定化策を提言していたが、私の政策提言を政府・自民党が取り上げたのは、事態が急変し、このままでは如何ともしがたい状況になってからであった。
金融システム不安は経済の「危機管理」がわが国から抜け落ちていたことに原因があった。最大の危機管理とは、いうまでもなく国民の生命と財産、国土にかかわる安全保障である。金融の危機管理にしくじっても、あるいはやり直しができるかもしれない。しかし安全保障の危機管理に失敗すれば、間違いなく国民の血が流れ、失われた命が再び戻ることはないのである。
「安保の常識」と「国内向けの論理」の使い分け
国会でガイドライン法案をめぐるいささか低調な論戦が続いていた三月下旬、東西で二つの事件が起こった。ひとつは米国はじめ北大西洋条約機構(NATO)軍による、ユーゴスラビア連邦コソボ自治州問題をめぐっての武力行使である。もうひとつは朝鮮民主主義人民共和国(北朝鮮)の不審船舶によるわが国領海の侵犯事件であった。このふたつは、規模も性格も全く異なるとはいえ、日本人には極めて重要な教訓を与えてくれている。
日本の防衛は、いうまでもなく日米安全保障条約に基づく日米同盟関係を機軸にしているが、その米国の国際軍事戦略は、冷戦後、大きな変化をみた。すなわち旧ソ連を仮想敵国とする「ソ連封じ込め」から、地域紛争、民族紛争の予防、対処を中心とする「地域安定化」への転換である。世界規模の戦争から地域レベルの戦争への対応に、発想を変えたといってもいい。現戦略において、米国の軍事力は、同時に別の地域で発生する二つの戦争(二人の『ならず者』)に対応しうる能力を保持することを基本にするとされる。このうちのひとつは、主として中東を想定したものであっただろう。今回のコソボは国家間の戦争ばかりでなく、現状を放置すれば大量の住民が虐殺されるという判断のもとに、いわば第三国の市民保護にまで踏み込んだものであった。
ただ、事柄の性格は異なっても、そこから遠く離れたもうひとつの地域の不安定要因といえば、現時点では朝鮮半島を想起せざるをえない。
北朝鮮の不審船舶の動きを、コソボの危機と連動した挑発、あるいは「日米安保体制に探りを入れた」とみるのは深読みにすぎるが、領海を侵犯された当事者の日本としては、最悪の事態を考え、対応していかねばならないのは当然だ。確かに米国が、世界で最も心強い友邦であることは疑う余地はない。明治の日本が当時の世界最強国だった英国との同盟によって、黎明期の拠り所を得たように、戦後五十年以上にわたる平和と安定は日米安保によってもたらされた。
ただ、コソボに対する米国の苦悩ぶりを見れば、軍事的な能力はともかく、政治的な問題として、「もうひとつの紛争」にまで介入することが可能だろうか、という疑問を払拭できまい。日本に直接、ミサイルが撃ち込まれるとか、朝鮮半島で武力衝突が起きるといった事態にまでなれば、話は別だ。米国はその威信にかけても二つの戦争を戦い抜こうとするだろう。反面、今回の領海侵犯から想起されるテロとか麻薬、密輸、武装難民の流入といった後方撹乱戦術、いわゆる低強度紛争であった場合、「それは日本自身の問題だ」と思うのが、米国の国民感情からしても自然ではあるまいか。しかし、今の日本はそうした事態への準備が制度的にも、精神的にも何らなされていないのである。
私は今回のガイドライン法案の審議を通じても、日本の安保論議の虚構性を感じずにはいられない。たとえば、周辺事態法をみても、あたかも日本は「安全な場所」にあるという前提に立って、出撃する米軍にどのような後方支援を行うのか、という詳細な規定を置いている。しかし、現実問題として、周辺事態が発生すれば、米軍の基地があり、これを支援する日本は、直接的な攻撃対象になりうるのである。つまり周辺事態は、わが国自身の有事と密接不可分な関係にある。
日本の有事となれば、誰しも日米安保条約第五条に従って、米軍が出動すると考える。ところが現実には、その時、自衛隊が米軍を支援する協定も法律も存在しない。周辺事態が、日本有事に発展したとたんに、対米支援のための根拠がなくなるという奇妙な事態になるのである。
これは逆の場合でも同じである。ある日突然、日本国内の米軍基地を目標に、他国からミサイルが発射されたとする。周辺住民にも大きな被害をもたらすのは確実だ。にもかかわらず、今のままだと政府は、これを日本に対する「組織的、計画的」な武力攻撃であるか否かの議論に時間を費やす可能性が大きい。一方の米軍は直ちに反撃に出て、ガイドラインに基づく自衛隊の支援を求めるだろう。結局、政府は日本国民が殺傷されているのに、「自衛権の発動」ではなく、「対米支援」として自衛隊を出動させるという本末転倒な結果を招きかねないのである。
こうした矛盾は、安保の専門家も、国会で答弁している官僚諸君も、十分に承知している。にもかかわらず、虚構の論理がまかり通るのは、国会対策の必要上、「安保の常識」と「国内向けの論理」を使い分けせざるをえないからだ。この虚構を打ち破るのは、ひとえに国民の負託を受けた政治家の責任である。
誰にでも分かる「二本柱」の防衛
私はこれまでの訓詁学、解釈論のような安保論議を弄するのをやめ、誰にでも分かる「二本柱」の防衛を主張したい。一本目の柱は、いうまでもなく日米安保体制である。日本が他国による全面的な侵略行為に直面したり、地域の安定と平和に大きな影響をもたらすような紛争が起こった場合には、日米同盟で対処するしかない。ガイドラインもこれに実効性を与えるための一つの手段だ。
ただ、日本が自力で国を守るメカニズムと意識なしには、日米安保も絵に書いた餅にすぎない。自衛という二本目の柱があってこそ、日米安保も初めて血の通った国の安全を確保できるシステムになる。先に述べた地域の紛争が日本の国土に軍事的に波及するケースや、日本の安全を脅かすテロ、挑発行為には、自ら立ち向かっていかなければならない。自分の国を自分で守ろうとしない国を、他国が守ってくれることなどありえない。「われわれには制度、法律の限界があるから、日本のために米国の若者に血を流してほしい」などと誰がいえるだろうか。
米国も自国の国益のために日米安保体制を選択しているわけだから、日本からみれば、時には「これは米国のための行動だろう」と映るケースもないわけではあるまい。その時、われわれは日本の国益に照らして、冷静に総合的な判断を下す必要がある。もともと日米安保において、米国は日本を守る義務があるが、日本に米国を守る義務を課せられているわけではない。この片務性に、国家間の約束の基本である双務性を与えるためには、日本よりも米国の利益の方が大きいと思われる場面でも、国際社会の正義に反しない限り協力していく姿勢が重要だ。
以下、日本の自衛のために最低限必要なメカニズムとは何かを詳述する。
最悪の事態を想定し、これに備えるには、五十年間にわたって空白だった法律と制度の穴を埋める必要がある。その処方箋として次のようなシステムを提唱する。
第一に安全保障・危機管理に対する基本原則を定めた「危機管理包括法」を制定する。危機にあたっては最高責任者たる内閣総理大臣に権限を集中することを明確にし、指揮命令系統を確立する。危機管理を必要とする事態には大災害や生物化学兵器によるテロ行為なども含むことにする。
第二に日本を騒乱状態に陥れようとする、あるいは混乱を引き起こすことで利益を得ようとしている邪悪な意図を有する集団からのテロ行為など、有事と平時の間の「グレーゾーン」に備えた研究を進め、対応策を検討する。
第三に危機が現実になった場合に備えて自衛隊、警察を中心とする公的機関と、医療、通信関係、地方自治体までを網羅した「対処実行計画」を整備する。国民ひとりひとり、民間の企業体との連絡・協力体制も検討しておくことが重要だ。
第四に自衛隊を危機管理対応の中核と位置付けるべく、装備を見直して公共財として活用する態勢を整えるのである。
具体的に論考してみよう。
危機管理包括法で危機管理を必要とする事態としては、国内における大規模災害、わが国に対する武力攻撃、テロ攻撃など有事と平時の間にある「グレーゾーン」の事態を対象とする。現在、政府部内で研究を進めている有事法制は改正を要する関連法案が膨大な数に上がるうえ、基本的には日本有事を想定した法的措置となっている。まずは各種事態に備える一つの基本法を整備することが何よりも重要だ。そして国民の生命、財産にかかわる非常事態に際しては内閣総理大臣を最高責任者、指揮官とする指揮命令系統を確立する。総理に事故あった場合をも想定し、指揮命令権の継承順位も明記する。危機にあたって迅速に対応するには、何よりも決断、指揮、責任の所在を明確にしておくことが必要だからだ。
第一の決断は政治の責任で行い、いかなる結果を招来しようと政治、すなわち総理大臣が最終責任を負う。これがシビリアン・コントロール(文民統制)の要諦で、重要な原則でもあるはずだ。制度や法律が整備されていないから、第一線の現場、部隊はもっとも大切な初動の段階で行動を躊躇してしまう例が少なくない。指揮命令の系統があやふやで、政治が、総理大臣が決断と結果責任を負うシステムを確立しないことこそ、わが国危機管理の大きな空白となっている。
指揮命令系統の問題については、私には些かの経験がある。橋本龍太郎内閣の官房長官を拝命した直後から、阪神・淡路大震災のことが脳裏を離れなかった。もし東京に大地震が起こり、不謹慎な想定だが橋本総理本人が地震の犠牲者になってしまったら、だれが職務を代行するのか。事務当局の答えは「実は何も決まっていません」というものだった。
そこで手掛けたのが「首都直下型大規模地震発生時の内閣の初動体制」というマニュアルである。総理に事故あった場合は、一に副総理である閣僚、二に官房長官、三に国土庁長官、四にその他の閣僚の順番で総理の職務を代行する。閣僚が集まる場所は総理大臣官邸、次に国土庁、三番目に防衛庁中央指揮所、四番目に立川広域防災基地とする。閣僚は道路利用が可能なら緊急パトカーを活用する。ヘリコプターが使えるのならばヘリを利用する。道路が使えないなら、利用可能なあらゆる手段、徒歩でも自転車でもよい、とにかく集まる。緊急災害対策本部の設置が必要な場合は、連絡のとれる閣僚に電話などで了解をとって閣議決定を行う。連絡のつかない閣僚がいれば、事後速やかに連絡をとることとする、などの一連の緊急手続きである。極めて初歩的なマニュアルかも知れない。それでも、最低限の危機管理マニュアルがまったく存在しないことに比べれば、小さいながらも第一歩を踏み出すことはできた。私のときは内閣発足から一カ月以上が経過した一九九六年二月二十三日に閣僚懇談会で申し合わせたが、その後はいずれも初閣議で同様の申し合わせが行われている。
九七年一月には日本海でロシア船籍タンカーによる重油流出事故が起こり、環境破壊が懸念された。このときも私は各省庁に指令を出すための専門的な調査を実施し、実行プランをつくる専門家が内閣にいないことを痛感した。そこで検討を指示したのが危機管理専門監の設置だ。土石流や重油の流出などの事故への対応は、えてして省庁間のエアポケットに入りがちだからだ。この内閣危機管理監制度は一年後の九八年四月に実現し、動き始めている。
危機管理マニュアルの作成、危機管理監創設に至る事例は、ひとつのことを教えてくれる。官僚システムは、政治が決定を下してひとたび前例をつくれば、それ以降は自動的に前例を踏襲していくという事実だ。政治の決断による危機管理体制の確立が欠かせないと私が訴える背景には、この経験もある。
ある日突然起きる目に見えない危機
冷戦が終わったいま、日本有事などというきな臭い事態が起こるはずもない、という意見をよく聞く。ソ連という国が消滅したため超大国が大規模に侵攻してくるというシナリオは無くなった。しかし、東西両陣営という歯止めがなくなったことは、「明白かつ差し迫った危機」にかわり、「ある日突然起こる目に見えない危機」を身近に引き寄せてしまったとも言える。テロや生物化学兵器は、その好例である。これは決して想像の世界の話ではない。わが国で四年前にほぼ連続して起こった二つの問題は、いかに日本が平和な国家であろうとも「あり得ない」という言葉こそ「あり得ない」ことを教えてくれる。
一つはオウム真理教による地下鉄サリン事件だ。先進国の首都で白昼、地下鉄に大量に毒物が撒き散らされ、尊い人命が失われた。わが国はこの事件を「一部の狂信者たちが起こした特殊な事件」と位置づけ、二度と起こらないケースとして例外扱いし、安心してしまってはいないだろうか。そうではなく、地下鉄サリン事件を邪悪な意図を持つ集団の生物化学兵器によるテロが現実のものになったと見て、これを貴重な教訓として封じ込めと機敏な対応策の立案に全力をあげるべきなのだ。地下鉄サリン事件は、生物化学兵器が国家的な規模でなくとも、簡単につくれることを世に知らしめたのである。
もうひとつは阪神・淡路大震災である。「倒れることはあり得ない」と信じられてきた高速道路は倒壊し、水道や電気、ガスなどのライフラインは途絶し、一挙に五千人を大きく上回る死者を出す大惨事となった。当時も自衛隊の初動の遅れや危機管理の不備が盛んに叫ばれた。このときも私は「ひとり内閣や官僚、自衛隊の問題ではない。われわれ政治家の準備不足がもたらした惨禍だ」と発言した。付言すれば政治家も、国民も、と言うべきかもしれない。
われわれが経験したこの二つの事象だけではない。想像するだけでも多種多様の危機が存在している。幾つか例をあげてみよう。
日本には数多くの原子力発電所がある。飲料水をたたえるダムがある。石油を備蓄するタンク、ガスタンクがある。日々の経済活動においてなくてはならぬものとなったコンピュータ回線、電話回線がある。例えばある邪悪な意図を持った集団が日本国内を混乱に陥れようと貯水地に毒物を混入したり、武装して原発や石油タンクに立て籠ったらどうなるか。あるいは地下鉄サリン事件と同様に、毒物やウイルスを携行して公共施設に人質をとられる悪夢も考えられる。私の旧軍時代の経験から言っても、敵の戦意を喪失させるには後方攪乱作戦で反基地闘争を起こす、非協力の機運を相手国内に広げる、社会を混乱状態に陥れるというのは、いわば常套手段だった。
今備えなければならないのは、こうしたある種の「古典的」なテロ活動だけではない。情報通信の発達した現在において、コンピュータ回線、電話回線を破壊して金融システムに甚大な被害を与え、経済活動を停滞させるのは簡単だ。これら複数の手段を併用し、同時多発的なテロを仕掛けたら、日本の安全はひとたまりもない。四方を海に囲まれたわが国では、不審船舶や武装難民の流入、麻薬など非合法物質の密輸、海洋汚染を目的とした環境破壊型のテロも念頭におかねばならない。「危機」と「脅威」は、枚挙にいとまないのである。
冷戦が終わったということは、多種多様の危機、脅威が拡散したと考えた方がよい。武器製造に関する技術は拡散し、国境を越えたヒトとモノ、技術の交流は、少人数のグループや単独行動であっても、生物化学兵器の製造や経済活動を混乱させる電子的なテロを起こすことを可能にしてしまった。
翻ってわが国の現状はといえば、心もとないばかりである。これらの新型のテロ行為への研究 、対応は他の先進諸国に比べても立ち遅れていると言わざるを得ない。公的機関も民間も、利害の絡む個別の問題についての危機感はあるのかもしれないが、全体を俯瞰するシステムも機関も存在していない。危機に一度陥れば、それは連鎖してしまう。これからの時代はただ無事を願っているだけではすまない。まずはあらゆる危機と脅威について、現時点で考えられる問題点を洗い出し、研究して整理する作業が必要だ。
自衛隊を公共財として活用せよ
目に見えない危機・脅威=広義のテロ行為の整理・研究を進めるとともに、自衛隊、警察、消防、海上保安庁などの公的機関が連携するマニュアルとなる対処実行計画を準備する。この実行計画には地方自治体やNTTなどの通信業者、緊急医療体制から住民との通信・連絡、協力体制も明記しておく。大規模な自然災害に備えた行動計画のようなものを、わが国有事や、有事には至らないが重大な危機を生じる「グレーゾーン」の事態に関しても整備するのである。併せて低強度紛争への対応を視野に入れた装備の調達を急ぎ、必要があれば組織の編成を見直す。現状では自衛隊法をはじめとする最低限の法整備はなされているとはいえ、実行を担保する仕組みは何ひとつ整っていないと言って過言ではないからである。
通信・連絡体制とは、何も高度なものでなくともよい。住民は不審な船や集団を目撃すれば、近所の派出所に届け出、通報する。派出所から警察に連絡を上げるとともに、警察はまず地方レベルで自治体、自衛隊の駐屯地、消防などと連絡を取り合う。組織ごとに緊急危機管理事態の連絡通信ポストを指定してもよいだろう。そして地方レベルの連絡が各組織の中枢にも上るよう、縦横十文字の情報通信体制を整えておくだけで対応は格段に違ってくるはずだ。医療のバックアップ態勢も整える。国民も「いざという時にはこれだけの組織が動き、守ってくれる」と分かれば、自然と地域の連帯感、安全保障への意識が芽生えてくる。個人の力に限界はあっても、力を合わせれば危機を乗り切ることができるという社会意識が育てば、公益を重んじる風潮も生まれてくるはずだ。自衛隊や警察、自治体と民間が一体となっての訓練の実効性も上がるのである。
もう一つの柱は、自衛隊を公共財として社会にきちんと位置付け、積極的に活用しようということだ。前述した有事と平時の間にある、新しいタイプの危機に備えるには、自衛隊の知識や経験、自己完結で部隊を運用できる能力が欠かせない。自衛隊は一年間で約五兆円もの国費を防衛関係費として投じている組織である。損得勘定から言っても、有効利用しない手はないはずだ。
ただ、私は闇雲な防衛力増強論や勇ましい自主防衛論には与しない。冷戦下における旧来型の武力侵攻に備える装備、兵器の水準から言えば、自衛隊は既に世界のトップレベルにある。しかし、冷戦が終わった今、果たして一千両にも及ぶ戦車が必要だろうか。今年度も高価な九〇式戦車が十七両、予算に計上されている。大規模な武力侵攻の可能性が遠のいたいま、自衛隊はいかなる「敵」から国民の生命と安全を守るべきなのかを真剣に考えるべきだ。冷戦後の新たな「敵」とは、言うまでもなく先ほど述べた「ある日突然に起こる、目に見えない危機」であるはずだ。この点を真摯に説明する努力をしなければ、自衛隊への信頼は高まらない。そこで私はまず緊急性の高い新たなタイプのテロ行為その他に備えた装備を優先した方がよいと考える。必要とあれば、防衛力整備計画に定める兵器・装備の購入を暫時、停止してもよいだろう。
しかし、大切なのは実は装備などのハードウエアではない。危機に対応するには人間関係や信頼関係を普段から構築しておくことが欠かせない。国民と自衛隊の間に「信頼」という名のソフトウエアを築く環境を、平時にこそ進めておく必要がある。
発足当初から激しい賛否両論の渦中にあった事情もあり、自衛隊はいざという時には後からの批判をおそれて抑制的に行動する傾向がある。阪神・淡路大震災の際には「初動が遅い」との批判が絶えなかった。地下鉄サリン事件でも、自衛隊の活動がもう少し早かったら、との指摘もあった。しかし、なぜ危機管理で最も重要な初動において立ち遅れるのかは、自衛隊の心理というソフト面を考える必要がある。
たとえば先述した有事には至らない「グレーゾーン」の危機が勃発したとしよう。これは一義的には警察が対応する。自衛隊の本格活動は治安出動を下令してからのことになる。この間には現在、法に隙間がある。その隙間をぬって、自衛隊が出動しようとすれば、おそらくは災害派遣の規定を準用するほかない。この場合、仮に阪神・淡路大震災の時と同じく、もし大惨事だったなら「なぜ直ちに自衛隊は出動しなかったのか」との批判を浴びるだろう。逆に事態が思いのほか軽微だった場合には「権限を逸脱した活動だった」との非難にさらされる。言いかえれば突発事態に遭遇した部隊は、本来ならば政治のとるべき結果責任のすべて背負う覚悟で活動しなければならないのだ。これは現場の指揮官、部隊にとってあまりに酷な話しだ。「法や制度の整備は後回しでよい。現行法の運用で十分に対処できる」との意見は、実際に危機管理の行動にあたる者がさらされる、この強烈な心理的ストレスを見落としている。阪神・淡路大震災での「初動の遅れ」も、多分にこの心理的ストレスが影響していた。
戦後の自衛隊は戦前の旧軍とは本質的に異なる。自衛隊の権限を逸脱した行動を心配するより前に、致命的な初動の遅れを招かない体制づくりを優先しなければならない。自衛隊の権限乱用への懸念は、決断と責任を伴うシビリアン・コントロールの徹底であり、指揮命令系統の確立であり、平素からの対処実行計画をもとにした訓練を通じた民間と自衛隊の融和と信頼関係の確立という先に提唱した三つの施策の実現によって十二分に払拭できるものと考える。
総理を最高責任者とする危機管理総括法
先日も法と制度の空白を突かれるような事態が起こった。北朝鮮の不審船舶によるわが国の領海侵犯である。自衛隊が発足して初めて海上警備行動を発令したこと自体は評価していい。しかし、不審船舶を取り締まる根拠法はない。海上保安庁は漁業法や海上汚染防止法を適用して対応するのが精一杯なのだ。海上自衛隊にしても、相手から攻撃を受けない限り、警告射撃以外の武器使用はできない。攻撃を受けて武器使用する場合も、急迫不正の侵害に対する正当防衛、緊急避難が要件になる。つまりは「威嚇のための威嚇」で終わりかねないのだ。
昨年には北朝鮮の弾道ミサイルが日本列島を越えて発射される事件もあった。これも重大な問題を惹起している。現行法の体系では、総理大臣が防衛出動を発令できるのは「武力攻撃の恐れがある場合」とされている。しかし、弾道ミサイル攻撃の恐れありとして防衛出動を下令しても、それだけでは実際に迎撃するための武力行使はできない。なぜか。武力行使をするには、武力攻撃が発生していることが必要だからだ。これはとりもなおさず自衛権発動の要件にほかならない。
しかし、武力攻撃とは一体誰が認定するのか。現場の自衛官なのだろうか。そもそも防衛出動とはどのような手続きを経て発動されるのか。わずか数分で飛来してくる弾道ミサイルへの対抗手段を瞬時に判断する仕組みは、実は何も整っていない。安保専門家たちに問うても明確な回答は得られないのが実態なのである。
この一年以内に起こった安全保障にかかわる二つのケースの経験に学ぶことが重要だ。領海、領空侵犯に対しては、断固たる自衛措置をとる。国際慣習法に従って手続きを踏んで退去を命じ、必要とあれば機能を破壊するための直接射撃も辞さない。弾道ミサイル防衛にあたっては、第一撃の決断を下すのは、自衛権を発動するという重みと責任を考えれば総理大臣以外にはあり得ない。実際の対抗手段を取るには数分しかないというなら、細部は部隊に委任するとしても、発射の兆候をつかむなど一定の時点で事前に総理が決断すべきだろう。そのためにも、総理を最高責任者とする危機管理包括法が必要になってくる。先述したとおり武器使用の問題にしても、事態の進展を事前に想定した武器使用基準を作成し、総理が承認し、必要と認める場合には許可する仕組みが欠かせないだろう。
危機管理に際して総理に権限を集中するのは、権限濫用の危険がつきまとうとの懸念もあるだろう。しかし危機はある日突然にやってくる。事態への対処が適切だったか否かは、決断を下した総理たる政治家が職を賭して責任を明らかにすることで対応できるはずだ。政治のリーダーシップとはまた、責任をも併せて引き受けるのが当然だからである。
苦い記憶がよみがえる。
九七年七月、カンボジアが不穏な情勢に包まれた際、橋本内閣は邦人救出の目的でタイのウタパオ基地に自衛隊のC130輸送機を三機、派遣した。派遣にあたっては自衛隊法百条の八を根拠として認められる「準備行為」の範囲内の行為と判断してのことだったが、当時与党を組んでいた社民党などから手続きの問題があるのではないか、あるいはなぜここまでやる必要があるのか、との批判を頂戴したことがあった。
このとき、私の胸中を去来していたのは、「在外邦人を守る具体的な例を早く作らなくてはならない。掃海艇の時とは違って、今度はたくさんの日本人の生命がかかる由々しい問題だ」との思いであった。当時の橋本総理と話し合ったのは「法律の範囲内で決断し、責任を負わなければならない」という一点である。橋本総理が決断した措置は、幸いにして自衛隊機が実際にカンボジアへ邦人救出に赴くことはなくして終わったが、海外に自衛隊機を派遣した以上、何が起ころうとも最終的な責任をとる覚悟だけは、私も橋本総理も決めていたのである。
同時に記憶によみがえったのは、湾岸戦争後に掃海艇をペルシャ湾沖に派遣した際の出来事だった。私は自民党の国会対策委員長を務めていたが、各党と折衝を重ねても、なかなか了解を得られない。そこで各党関係者の方々に「昔、『船は出て行く煙は残る』という歌があったが、今度は『船は出て行く議論は残せ』にしましょうよ」と呼びかけた。掃海艇が帰国したら、今後日本はどのような行動がとれるのか、法律には何と何を整備しておけばよいのかについて互いに議論し、研究しようではないか、という問題意識だった。ところが、掃海作業を実施して帰国してみると、国内世論は支持し、称賛の声が上がり、一件落着とばかりに議論は深まらず終わってしまった。官房長官時代には、ただ責任を取ると覚悟を決める以外、何もなす術のなかった在ペルーの日本大使館人質事件もあった。
振り返ってみれば、安全保障や危機管理に直面する事態に何度も見舞われ、その都度論議を巻き起こそうとした私の試みは、いずれも泡のごとく消え去ってしまった感がぬぐえない。それは私の力の至らなさだったかもしれない。あるいは幸いにして大事には至らなかったことが大きいのかもしれない。しかし危機はある日、突然にやってくる。危機を察知する本能が衰えてしまった現代の日本にあって、その結果がこれまでと同じく「大過なく無事」で終わる保証と必然性はどこにもないのである。
ある軍事専門家の説によると、アングロサクソン系国家の強さは、過去の失敗を恥とはせず、失敗に学んで次への経験とすることだという。日本の戦前の士官教育は、この逆であった。戦勝のケースを教材に、勝利の栄光だけで志気を鼓舞し、敗北に学ぶ勇気を忘れていたのである。今の日本も、本質的にこれと変わることはないとしか思えない。
安保や危機管理について述べてきたが、国が他国との利害関係を調整する最大の手段は、いうまでもなく外交である。現代の国際社会にあって、武力を背景にした威嚇的な外交はもってのほかだが、自衛の裏付けのない外交も、空虚だ。ところが今の日本には、自分が敵意を持っていなければ、相手も過激な行動に出ることはない、という楽観主義がはびこっている。個人としてならそれでよくとも、国としてはそれで済む話ではない。私の官房長官時代、ガイドラインには「台湾海峡も含む」と発言したとして、大問題になったことがあった。正確にはそうは言っていないのだが、私の本意はこうである。この直前に当時の自民党首脳が訪中し、中国側に対してガイドラインは「朝鮮半島を念頭に置いている」と説明した。確かにわれわれの頭の大部分を朝鮮半島が占めていることは間違いない。当人は外交官時代から中国の専門家であったし、「日米中の正三角形関係」を主張するほど、中国との関係を大事に考えている人だから、中国の懸念を解消しなければならないと思ったのだろう。
しかし、安保の観点からすれば、これは困った問題であった。ガイドラインは朝鮮半島を念頭に置いているといえば、ではそれ以外は違うのか、ということになる。私は「二つの中国」を認めるものでは決してないし、台湾問題は中国人同士が話し合って解決する問題だと認識しているが、中国が台湾武力解放の選択肢を依然として放棄していない以上、日本が「どうぞ、おやり下さい」というメッセージは絶対に発信できないのである。誤ったメッセージが、後から考えれば回避できた紛争を招いた例はいくらでもある。政権党の首脳のメッセージをそのままにしておけば、やがてそれが日本政府全体のメッセージだと解されてしまうことを、私は恐れた。国家が国の脅威とか危機を考えるにあたり、あらかじめ「これはない」と排除することはできない。ところがいったんこのパンドラの箱を開けてしまうと、これを再び箱の中に閉じ込めることはなかなかできない。ガイドラインをめぐる日中の確執も、完全に予防することは無理であったにしても、ある程度弱める方法はあったかもしれない。
ガイドラインには日米同盟という国家の戦略の部分がある。反面、ここで私が提唱した自衛論は、国家としての基本的な基盤である。日本の国家戦略が、他国の国家戦略にとってはマイナスとなる場合、台湾問題のような論争を起こすことは避けられないかもしれない。これを調整するのが外交の役割だ。ただ、自衛という当然の基盤なしに、外交ですべてを調整しろというのは、面も籠手もつけずに剣道の試合に臨めというに等しいのである。
国民の愛国心を基盤とする自立した精神
もう一度、冒頭の米国旅行に戻る。その二十年前、十七歳だった私は茨城県の旧制太田中学を卒業し、軍人になるべく陸軍の予科士官学校に入学した。終戦時には旧満州で、戦闘機の操縦訓練をしていたから、米軍と一線を交えたことはない。テネシーで私をもてなしてくれた家の主人は私より年配だったが、もしも時期と場所が少しずれていれば、敵と味方で向かい合っていたかもしれない。その主人は医者で、もちろん職業軍人ではない。ただ、いったん国の危機が起これば、家族団欒のギターを銃に持ち替え、国と民主主義と家族のために、戦場に赴くのが、米国の市民である。
いつだったか、テレビの真珠湾特集番組で、ブッシュ前米大統領のインタビューを見たことがある。「日本の真珠湾攻撃があった昭和十六年の十二月七日、あなたは何をしていましたか」という質問に、ブッシュ氏はこう答えた。「ボストンの大学の構内を歩いていて友人から真珠湾攻撃を聞いた。大変なことになった、と思った」。そして、青春を謳歌していた学生生活を止め、軍隊に志願したのである。ダンスやデートを楽しむ若者が、強制されたわけでもないのに、明日をも知れない兵士となる。確固とした生活規範のもとに、教会と社会に奉仕する精神をたたき込まれた米社会の特質であり、民主主義の原点である。
九七年、沖縄の駐留軍用地特別措置法の改正騒動に際し、私が痛感したのも、社会への奉仕、すなわち公益への貢献と、沖縄の「県益」あるいは個々人の私益との兼ね合いだった。確かに今は平和な時代だ。しかも戦中戦後と、どこの県民よりも辛酸をなめた沖縄の人たちに「公益のために県益、私益を捨ててくれ」というのは辛く、酷なことだった。われわれが沖縄の人々にそう言える資格を持つ方法は一つしかない。政治家を含め、すべての国民が自らの生活と力量の範囲内で、公益に奉仕することである。
私が本稿で述べた安保論は、突き詰めれば国民の愛国心を基盤に、自立した精神で国を守ろうと訴えようとするものである。実のところ、私は旧軍の出身であるがゆえに、できることなら安全保障の問題には立ち入りたくない、という気持ちが強かった。戦争で廃虚になった故郷を再建するのは経済であり、技術だというわけで、大学は工学部の土木学科を選び、卒論は「日立港の開発と茨城の未来」である。政界に入ってからも、日本の産業振興やエネルギー開発に大きな喜びを見いだした。経済発展だけを追求すればいいという時代性と、東西冷戦構造によって逆に庇護された日本の国際環境が、これを許容したともいえる。冷戦は終わって久しく、時を同じくして崩壊し始めた日本の右肩上がりの経済システムも、病膏肓に入っている。ここでもう一度、自立という国の原点に戻らなければ、日本の安全も経済の再建もあり得ない、というのが今の私の実感である。
若い議員の中には「おじいちゃん、それは古いよ」と言ってくる人もいる。そういう若い世代には、実は、日本の安保論議の虚構に疑問を感じ、新しい論を打ち立てようとする気概のある人が非常に多い。それはそれとして、私の世代には、ここでものを言い、少しでも実行しておかなければならない責任がある。そう遠くない将来に、われわれのような戦争を体験した世代はいなくなり、政治も「戦後」の経験則だけで動いていく時代になるだろう。われわれが敗戦直後に経験した茫然自失、明日から何をすればいいのかも分からない虚脱感も語り継がれることはない。であれば、われわれの世代が残せることは、戦後の日本が積み重ねてきたものの中で、すでに負の遺産となったものを壊し、新しい芽の育つ礎をつくることにほかならない。惰性に流されて行なってこなかったことを、日本人は今、ひとつひとつ実行していかなければならないのである。